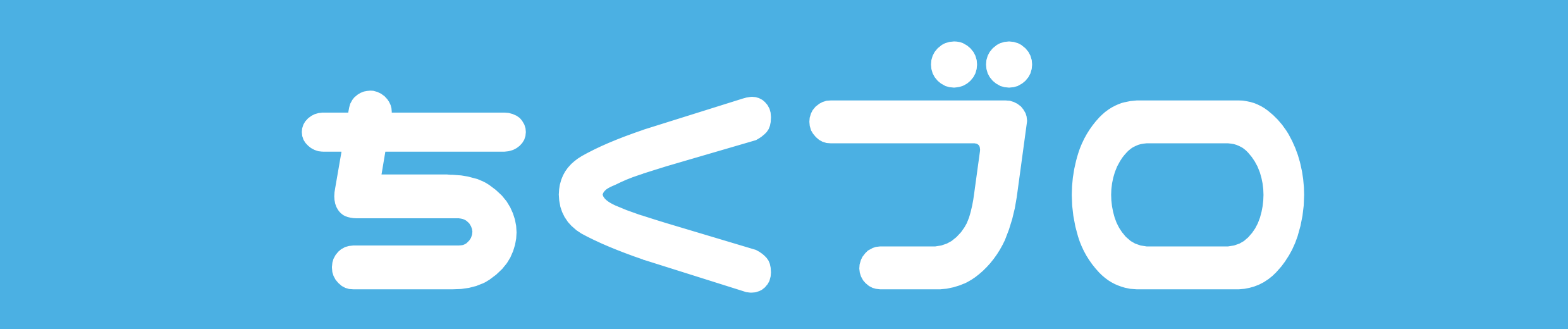ども!ちく(@chikuchanko)です。
今回紹介するのは奈良県奈良市にある興福寺です!
奈良市内にあるお寺でも、東大寺に次いで多くの観光客の人が訪れる人気スポットです!
観光ストリートからすぐの場所にあるお寺なんですよ〜
西国三十三所 第9番札所(南円堂)、南都七大寺 第2番札所、西国薬師四十九霊場 第4番札所(東金堂)、神仏霊場巡拝の道 第16番札所、大和北部八十八ヶ所霊場 第62番札所(菩提院)にもなっているお寺です。
早速紹介していきます!
※お詫び※
伺った時間帯の問題もあり、一部の写真は逆光での撮影になってしまったので、光が入り込んでいるものがあります。ご了承ください。
目次
寺の概要
- 御本尊:釈迦如来
- 宗派:法相宗
- 寺号:興福寺
- 創建:669年
- 開基:鏡女王
御由緒
興福寺は、669年に中臣(藤原)鎌足が重い病気に患った際、夫人である鏡女王が夫の回復を祈願し、釈迦三尊を安置するために造営した山階寺を起源とします。壬申の乱の後に飛鳥へ移築され、地名をとって厩坂寺となり、さらに平城遷都の際、710年藤原不比等によって移されるとともに「興福寺」と改号されました。
※興福寺の歴史より一部抜粋
実際の様子
南円堂から参拝!合わせて一言観音堂も!
興福寺境内へ続く場所はいくつかあります。
ならまち側から行ったので、南円堂のそばにあるこちらの階段から興福寺へ入りました。
この南円堂の階段周辺はお土産や食べ物屋さんが集中しているあたりでもあるので、かなり観光客で賑わっているエリアでもあります。
階段を上っていくと、右手に手水舎があります。
龍のいる手水舎で、柄杓は左側に用意されていると言う、珍しい手水舎でした。
そしてこちらが南円堂!
藤原冬嗣が父 内麻呂追善のために創建したお堂です。
西国三十三所のお堂でもあることから、特に参拝者が多いお堂なのだそう。
御本尊は不空羂索観音坐像です。
すぐ隣に一言観音堂があります。手前は藤棚になっており、このお堂の右隣には納経所もあります。
一言で願いを聞き届けて下さる観音さまがいらっしゃるお堂です。
 ちく
ちく
五重塔と東金堂
遠くからでも見える五重塔。国宝です。
光明皇后が建立した歴史ある建物ですよ~
中には入らないので、外観を楽しみましょう!写真の高さからもわかるように、遠くからでもこの五重塔のてっぺんが見える場所があります。
そのすぐ隣に同じく国宝の東金堂があります。東金堂はお堂内の拝観が有料です。
御本尊は薬師如来坐像。
聖武天皇が叔母 元正太上天皇の病気全快を願って作られたものです。薬師如来さまの他に、日光菩薩、月光菩薩、四天王や十二神将像など、たくさんの大きな仏像が並んでいるお堂です。
興福寺を代表する建物 中金堂!
興福寺のシンボル的存在 中金堂。
現在見ることが出来るこちらの中金堂は2018年10月に修繕工事が終了したばかりの新しいお堂です。
2000年に老朽化のため解体され、今再びこの地へ再建されたお堂なのです。
東金堂同様に、お堂内の拝観は有料です。
中金堂内には、興福寺の御本尊である釈迦如来をはじめ、その脇侍である薬上菩薩と薬王菩薩、四天王、大黒天と吉祥天とたくさんの仏像が並んでいます。
興福寺の宗派である法相宗の祖師たちが描かれた柱もあるんですよ~
中金堂の前からあたりを撮影した写真。
こちらは南円堂側です。
もう1枚。
こちらは五重塔と東金堂が写っています。
中金堂の拝観受付の隣に御朱印授与所でもある勧進所があります。
中金堂や東金堂など、この周辺のお堂の御朱印はこちらでしか頂くことが出来ません。
夕暮れの興福寺
せっかく奈良へ訪れたので、夜の奈良の街を訪れてみようと思い、興福寺周辺をちょっと散策しました。
夜の五重塔。ライトアップされていました。
中金堂は特にライトアップされていないので、暗くなると見えなくなってしまいます。
開門時間との違いは、お堂の扉が閉まっていること。
※実際には五重塔の写真と同じくらいの時間帯に撮ったので、もっと暗かったです。加工して少し明るくしています。
南円堂周辺。
こちらもひっそりとした雰囲気でした。
夜の南円堂近くの手水舎。
昼とは違うひっそりとした雰囲気に魅力を感じました。この雰囲気、結構好き。
興福寺の大きなお堂などはじっくり見学できましたが、こちらのお寺、今回の奈良旅行最後に訪れた場所だったので、電車の都合で国宝館(宝物館)など、見ることが出来ない場所もありました…
いつかまた訪れたい!そう思い、興福寺を後にしたのでした。
御朱印
興福寺は御朱印を頂く場所が2箇所あります。
1つは中金堂の近くにある勧進所、もう1つは南円堂近くの納経所です。
西国三十三観音の札所は南円堂近くです。
どちらの授与所でも御朱印は5種類あり、お願いした御朱印は全てその場で書いて頂くことが出来ます。
値段は1つ300円。
この他にも、菩提院でも御朱印を頂くことが出来ます。
今回私は菩提院には訪れていないので、御朱印を頂いていません。
興福寺勧進所で頂いた御朱印
勧進所で頂いた御朱印はこちらの2種です。
左が東金堂、右が中金堂の御朱印です。
それぞれお堂の名前が中央に墨書きされており、中央の印にそれぞれの御本尊の梵字が押されています。
こちらではこの他に宝物館の御本尊である千手観音、東金堂の御詠歌、お寺の名前の由来になった「令興福力」の御朱印を頂くことが出来ます。
※令興福力の御朱印は南円堂でも頂くことが出来ます。
南円堂の納経所で頂いた御朱印
南円堂の納経所で頂いた御朱印はこちらの3種です。
左から一言観音堂、令興福力、南円堂の御朱印です。
目の前で御朱印を書いているところを見ていたのですが、筆さばきがとても美しかったことが印象に残っています。
散華も頂きましたよ~!
西国三十三所の散華ですが、一言観音さまの御朱印と一緒に撮影しました(この位置が撮りやすかった)
この他に、南円堂と一言観音堂の御詠歌の御朱印も頂くことが出来ます。
限定御朱印情報
こちらのお寺では限定御朱印は登場しません。
アクセス
| 住所 | 奈良県奈良市登大路町48 |
| 電話番号 | 0742-22-7755 |
| 拝観時間 | 9:00~17:00 |
| 拝観料 | 宝物館 大人 700円/中高生 600円/小学生 300円
東金堂 大人 300円/中高生 200円/小学生 100円 中金堂 大人 500円/中高生 300円/小学生 100円 ※宝物館と東金堂の共通拝観券は大人 900円/中高生 700円/小学生 350円 |
| 御朱印受付時間 | 拝観時間と同じ |
| 駐車場 | 有料 |
| 最寄り駅からのアクセス | 近鉄線「近鉄奈良駅」より 徒歩5分
JR「奈良駅」より 徒歩15分 |
| 公式サイト | こちら |
合わせて訪れたい周辺の神社仏閣情報
奈良市の中心地にある「東大寺」「春日大社」など
同じ奈良市の中心地に奈良の大仏が有名な東大寺があります。他にも春日大社は周辺でも特に有名な神社仏閣です。
東大寺の境内にはその守護神である手向山八幡宮があります。近くに氷室神社があります。
春日大社の周辺には新薬師寺、不空院、白毫寺、奈良縣護国神社があります。
興福寺の近くには福智院や奈良町天神社や瑜伽神社、御霊神社、元興寺、十輪院、祟道天皇社、飛鳥神社があります。
他にも近鉄奈良駅の方へ行くと漢国神社や率川神社があります。
東大寺を北上すると般若寺や奈良豆比古神社があります。
その他の奈良の神社仏閣まとめ
その他の奈良の神社仏閣をまとめた記事はこちら!
奈良はちょっと遠いけど気になる、行ってみたい!と言う人は旅行へ行きましょう!
じゃらんnetはホテルや移動の新幹線、飛行機などを安く予約できる予約サイトです。ぜひ行く際は活用してみて下さいね〜
ちょっと贅沢な旅をしたい人には一休.comがオススメです!
![]()
アマゾンで本を購入して情報収集するのもおすすめですよ~!
広告
![]()
にほんブログ村