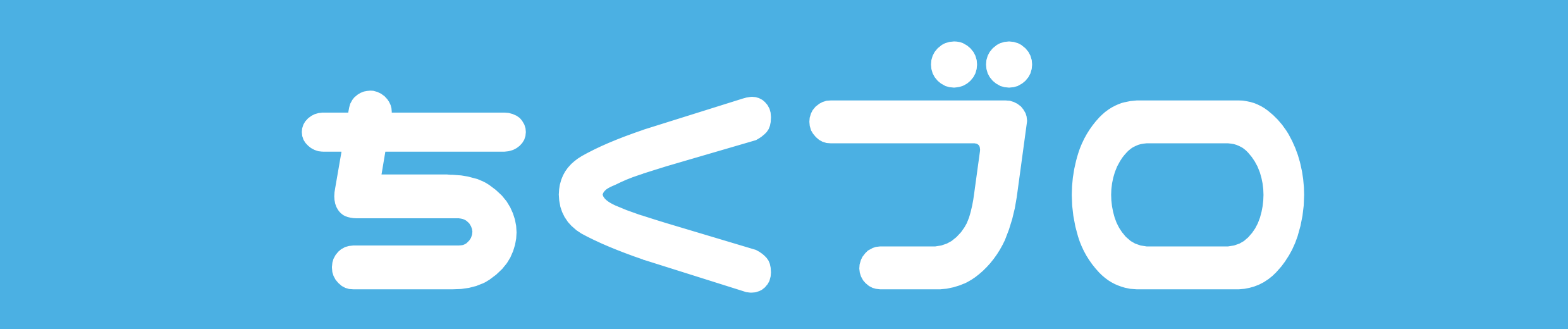ども!ちく(@chikuchanko)です。
今回紹介するのは京都 東山にある建仁寺です!京都五山の第3位のお寺です。
京都最古の禅寺で、臨済宗建仁寺派の大本山です。国宝の風神雷神屏風図があることでも有名です。
早速紹介していきます!
目次
- 1 寺の概要
- 2 実際の様子
- 3 御朱印
- 4 アクセス
- 5 合わせて訪れたい周辺の神社仏閣情報
- 5.1 東山にある「両足院」「霊源院」「禅居庵」「正伝永源院」「清水寺」「地主神社」「六道珍皇寺」「西福寺」「京都ゑびす神社」「安井金毘羅宮」「若宮八幡宮」「日體寺」「八坂庚申堂」「青龍寺」「法観寺」「高台寺」「圓徳院」「京都霊山護国神社」「銅閣寺」
- 5.2 祇園にある「八坂神社」「仲源寺」「知恩院」「青蓮院門跡」
- 5.3 京博近くにある「三十三間堂」「法住寺」「養源院」「豊国神社」「方広寺」「智積院」「新日吉神宮」「妙法院」
- 5.4 周辺にある「泉涌寺」「雲龍院」「来迎院」「新善光寺」「戒光寺」「即成院」「法音院」「今熊野観音寺」
- 5.5 東福寺周辺にある「東福寺」「勝林寺」「退耕庵」「一華院」「天得院」「同聚院」「正覚庵」「光明院」
- 5.6 伏見にある「伏見稲荷大社」「伏見神寶神社」「荒木神社」「石峰寺」「藤森神社」
- 5.7 その他の【東山・祇園】の神社仏閣をまとめた記事はこちら!
- 5.8 その他の京都の神社仏閣まとめ
- 6 旅ブログ「ちくとりんご」で新緑の京都旅レポ公開中!
- 7 旅ブログ「ちくとりんご」で10月の京都旅レポ公開中!
寺の概要
- 御本尊:釈迦如来
- 宗派:臨済宗建仁寺派
- 山号:東山
- 寺号:建仁寺
- 正式名称:東山 建仁禅寺
- 創建:1202年
- 開基:源頼家
- 開山:栄西上人
御由緒
日本に臨済宗を正式に伝えたのは栄西がはじめとされている。栄西は永治元年、備中国(岡山県)に生まれた。13歳で比叡山に上り翌年得度(出家)。仁安3年と文治3年の2回、南宋に渡航した。1度目の渡宋はわずか半年であったが、2度目の渡宋の際、臨済宗黄龍派の虚庵懐敞に参禅した。建久2年、虚庵から印可(師匠の法を嗣いだという証明)を得て、帰国する。当時、京都では比叡山(延暦寺)の勢力が強大で、禅寺を開くことは困難であった。栄西ははじめ九州博多に聖福寺を建て、のち鎌倉に移り、北条政子の援助で正治2年に建立された寿福寺の開山となる。
その2年後の建仁2年、鎌倉幕府2代将軍・源頼家の援助を得て、元号を寺号として、京都における臨済宗の拠点として建立されたのが建仁寺である。伽藍は宋の百丈山に擬して造営された。
創建当時の建仁寺は天台、真言、禅の3宗並立であった。これは当時の京都では真言、天台の既存宗派の勢力が強大だったことが背景にある。創建から半世紀以上経た正元元年には宋僧の蘭渓道隆が11世住職として入寺し、この頃から純粋禅の寺院となる。
※Wikipediaより引用
実際の様子
三門と明星殿
こちらはお寺の入口の門。三門とは別の門です。
ここから境内へ入りましょう!
進んでいくと、奥にチラっともう1つ門が見えてきました。
こちらが三門です。山門ではなく三門と書くお寺です。別名「望闕楼」と呼ばれています。
この三門は、静岡県にある安寧寺から移建した門です。三門とは、空門、無相門、無作門の三解脱門の略です。参拝客は通ることは出来ません。大きな三門を眺めて楽しみましょう。
こちらは三門の近くにある明星殿。
楽大明神が祀られています。
法堂内の御本尊と双龍図
こちらが法堂。別名拈華堂と呼ばれています。
法堂の天井に描かれているのが双龍図。
その下には御本尊がいらっしゃいます。
中央が御本尊である釈迦如来座像、左右には脇侍の迦葉尊者、阿難尊者です。
双龍図と御本尊を一緒に撮影。
いかに双龍図が大きいのか伝わると良いな…!!
法堂を外から見ることは無料で出来ますが、中へ入る場合は、一度本坊へ行き、拝観料を支払う必要があります。
私も法堂の外観を撮影したあと、本坊で拝観料を支払い、順路に従って法堂内へ入りました。
本坊入口で拝観料を支払い中へ!
本坊で拝観受付を済ませ、建仁寺の有料拝観エリアを満喫します。
まずお出迎えしてくれるのが風神雷神屏風図。本物ではありませんが、とても精巧に作られている複製版です。
この絵、昔教科書で見た気がする。
建仁寺で受付をする際貰えるパンフレットの表紙を飾るほど、このお寺の中でも有名な絵です。
 ちく
ちく
雲龍図
順路を進みます。すると、和室の襖にらは雲龍図が描かれていました。
通常公開されているこちらの図は、高精細デジタル複製版です。キヤノンの協力で複製され、常設で電磁されています。
方丈から見る大雄苑
更に進みます。すると方丈に着くので、ここから大雄苑と言う枯山水庭園を見ることが出来ます。
座って庭園を眺めることも出来るので、綺麗な和の景色に癒されたい人にオススメです。
方丈はぐるっと一周出来ます。奥に見えているのは納骨堂です。
大雄苑のちょうど反対側にあります。
◯△◻︎乃庭
こちらは◯△□乃庭。
◯△□の単純の3つの図形は、宇宙の根源的形態を示しており、禅宗の四大思想(地水火風)を象徴しているそうです。
小書院の襖絵
先へ進みます。すると小書院と言う部屋があります。
注目ポイントは、この部屋の襖絵。ベトナムの水辺の風景に着想を得て制作された襖絵です。
和室なのに異国情緒あふれる風景が描かれていて、なんだか素敵ですよね!
大書院の風神雷神図屏風
小書院の先に大書院もあります。ここにも風神雷神屏風図があります。
通常は高精細デジタル複製版を展示しています。つまり、こちらも本物ではありませんが、とても精巧に複製されていて、時代を感じる作品になっています。
四方全てが正面の禅庭 潮音庭(三連の庭)
先ほど紹介した小書院、大書院は、潮音庭という庭園を囲っている部屋です。
東西南北、どこから見ても正面になるようになっているのが、この潮音庭。四方のうち、小書院、大書院以外の二方は2つの部屋をつなぐ回廊になっています。
その回廊のうちの1つ。
更にこちらは回廊から見る庭園。
大書院から庭園を見た写真。
良い雰囲気ですね〜!風情を感じます。
扉を写さず、庭園だけを撮影。
新緑の季節のこの庭園、めっちゃ良い…!!!
回廊から見た庭園。
反対側の回廊からも撮影。
ほんと、いろんなアングルから楽しめるなぁ〜!
四方が正面になっている庭園で、新緑の青紅葉を満喫出来ました!
最後に、屋根瓦にもご注目。
「建仁」と書かれています。京都は屋根にもそれぞれの名前が書いてあるところが多いので、みたいで面白いです。
2018年10月に再訪!般若心経の写経とモシュ印アート!
5か月りの建仁寺へ!今回建仁寺を訪れたのは、写経をする為です。
建仁寺では誰でも気軽に般若心経を写経することが出来ます。
本坊で拝観受付を済ませ、御朱印専用窓口へ向かいます。そこで写経を希望すると1000円で写経をすることが出来ます。
写経をした際は、御朱印代はかからず、無料で御朱印を頂くことが出来ますよ!御朱印は本来、納経の証ですからね~!
写経をする専用の部屋で写経をしました。受付をすると、写経用紙と筆ペン、写経をする部屋までの地図や注意書きが渡されるので、まずは部屋へ向かいます。
座布団の敷かれた和室です。正座で般若心経をひたすら写経します。
他にも写経をしている方がいたので、写経し終えた用紙を、廊下で撮影!最後のほうには自分の名前などが書かれているのでこのような撮り方になっています。
一筆写経や、回向文の写経はしたことがありますが、般若心経のような長いお経の写経ははじめてでした。
足めっちゃ痺れました。
ずっと正座してたのですよ。約40分くらい写経に時間がかかりました。正座になれていないせいか、40分間の正座はキツかった。終わった後、しばらく立てませんでした。
でもその分、終わった後の達成感がありました。写経をすると、字を書くのが好きになります。
お手本を習い、綺麗になぞろうと言う気持ちで写経をするのですが、これに集中すると、一文字一文字と向き合えるので楽しいです。
普段から字を綺麗に書こうかな、と言う気持ちが生まれます。
写経を終えた後は、期間限定のモシュ印/コケ寺リウムの部屋へ!
この看板が目印です。
まずは苔のアートを楽しみましょう。
大雄苑。
◯△□乃庭。
潮音庭。
建仁寺境内の名所が小さな箱庭のようになっていてとても素敵でした。
そしてこちらがモシュ印!!
建仁寺の御朱印が、苔で書かれています!これ、めっちゃくちゃ大きいんですよ!駅とかに貼られてるポスターより大きかった。見ごたえがありました。
この苔イベントは2018年9月~11月まで開催されていました!
そしていつの間にかセルフ撮影スポットが出来ていました。
ここで撮影した写真はお手軽にプリントすることが出来る便利なシステムです。建仁寺境内の有料拝観エリアにいくつか設置されていました。
御朱印
御朱印は拝観受付をしてすぐの御朱印専用窓口で頂くことが出来ます。
御朱印帳を先に預けて帰りに受け取る流れになっています。オリジナル御朱印帳も用意されているので、気になる方はこちらも要チェックです!
2018年5月に頂いた御朱印
はじめての参拝で頂いた御朱印はこちら。
値段は300円。
「拈華堂」と書かれた御朱印です。法堂の別称で、元は「拈花微笑」と言う禅語からきています。
2018年10月に頂いた御朱印
2018年10月に頂いた御朱印はこちら。
限定御朱印情報
こちらのお寺では限定御朱印は登場しません。
アクセス
| 住所 | 京都府京都市東山区大和大路通四条下ル小松町584 |
| 電話番号 | 075-561-6363 |
| 開門時間 | 3月~10月 10:00~16:30
11月~2月 10:00~16:00 |
| 拝観料 | 大人 500円/中高生 300円/小学生 200円 |
| 御朱印受付時間 | 拝観時間と同じ |
| 駐車場 | 有料 ※拝観する場合は1時間無料 |
| 最寄り駅からのアクセス | 京阪電鉄京阪本線「祇園四条駅」より 徒歩7分
阪急電鉄京都線「河原町駅」より 徒歩10分 |
| 公式サイト | こちら |
合わせて訪れたい周辺の神社仏閣情報
東山にある「両足院」「霊源院」「禅居庵」「正伝永源院」「清水寺」「地主神社」「六道珍皇寺」「西福寺」「京都ゑびす神社」「安井金毘羅宮」「若宮八幡宮」「日體寺」「八坂庚申堂」「青龍寺」「法観寺」「高台寺」「圓徳院」「京都霊山護国神社」「銅閣寺」
建仁寺の塔頭寺院である両足院や霊源院、禅居庵、正伝永源院がすぐ近くにあります。中には通常非公開で特別公開する寺院もあります。
とても有名な清水寺には舞台だけでなく塔頭寺院や地主神社があります。
少し移動すると六道珍皇寺、六波羅蜜寺、西福寺、京都ゑびす神社、安井金毘羅宮、若宮八幡宮、日體寺、八坂庚申堂、青龍寺、法観寺、高台寺、圓徳院、京都霊山護国神社、銅閣寺があります。
祇園にある「八坂神社」「仲源寺」「知恩院」「青蓮院門跡」
東山区の一部である祇園エリアに八坂神社、仲源寺、知恩院、青蓮院門跡があります。
京博近くにある「三十三間堂」「法住寺」「養源院」「豊国神社」「方広寺」「智積院」「新日吉神宮」「妙法院」
京都国立博物館周辺に三十三間堂、法住寺、養源院、豊国神社、方広寺、智積院、新日吉神宮、妙法院があります。
周辺にある「泉涌寺」「雲龍院」「来迎院」「新善光寺」「戒光寺」「即成院」「法音院」「今熊野観音寺」
周辺に泉涌寺やその塔頭寺院である雲龍院、来迎院、新善光寺、戒光寺、即成院、法音院、西国三十三観音の札所である今熊野観音寺などがあります。
東福寺周辺にある「東福寺」「勝林寺」「退耕庵」「一華院」「天得院」「同聚院」「正覚庵」「光明院」
東福寺周辺に勝林寺、退耕庵、一華院、天得院、同聚院、正覚庵、光明院など数多くの寺院があります。
伏見にある「伏見稲荷大社」「伏見神寶神社」「荒木神社」「石峰寺」「藤森神社」
伏見周辺に伏見稲荷大社、伏見神寶神社、荒木神社、石峰寺、藤森神社があります。
その他の【東山・祇園】の神社仏閣をまとめた記事はこちら!
この他にも東山・祇園にはたくさんの神社仏閣があります。個別の記事にまとめたので、この周辺で寺社巡りをする際、ぜひ合わせてご活用下さい!
その他の京都の神社仏閣まとめ
その他の京都の神社仏閣をまとめた記事はこちら!
京都はちょっと遠いけど気になる、行ってみたい!と言う人は旅行へ行きましょう!
じゃらんnetはホテルや移動の新幹線、飛行機などを安く予約できる予約サイトです。ぜひ行く際は活用してみて下さいね〜
ちょっと贅沢な旅をしたい人には一休.comがオススメです!
![]()
アマゾンで本を購入して情報収集するのもおすすめですよ~!
旅ブログ「ちくとりんご」で新緑の京都旅レポ公開中!
こちらへ訪れたのは新緑が美しい5月。もう1つの運営ブログであるちくとりんごで、この時の旅行レポを公開中です!
ぜひこちらも参考にしてみて下さい!
参考
【京都旅行ブログ】2泊3日の京都旅行!新緑の季節の京都旅は超癒し #2ちくとりんご
旅ブログ「ちくとりんご」で10月の京都旅レポ公開中!
新緑の5月から約半年、10月の紅葉シーズン前にも再訪しています。この時の記事も書いているので是非参考にしてみて下さい!
参考
【京都旅行ブログ】美しい紅葉が色づく寸前!2泊3日の京都旅 #1ちくとりんご
広告