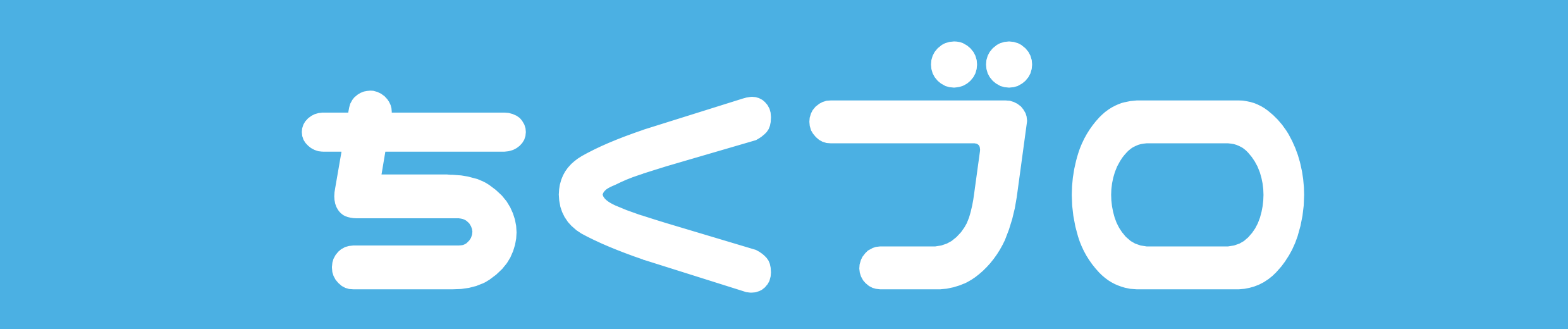ども!ちく(@chikuchanko)です。
今回紹介するのは京都 東山にある高台寺(@KodaijiFb)です!
清水寺から歩いていける距離にあるこのお寺は、豊臣秀吉の妻 ねねが秀吉の没後、その魂を弔うために建てられたお寺です。
今回は新緑の季節の青紅葉を観に行ってきました!
 ちく
ちく
早速紹介していきます!
▼高台寺の夜間ライトアップの様子の記事はこちら
目次
- 1 寺の概要
- 2 実際の様子
- 3 御朱印
- 4 アクセス
- 5 合わせて訪れたい周辺の神社仏閣情報
- 5.1 東山にある「清水寺」「成就院」「地主神社」「六道珍皇寺」「六波羅蜜寺」「西福寺」「建仁寺」「京都ゑびす神社」「安井金毘羅宮」「若宮八幡宮」「日體寺」「八坂庚申堂」「青龍寺」「法観寺」「圓徳院」「京都霊山護国神社」「銅閣寺」
- 5.2 祇園にある「八坂神社」「仲源寺」「知恩院」「青蓮院門跡」
- 5.3 京博近くにある「三十三間堂」「法住寺」「養源院」「豊国神社」「方広寺」「智積院」「新日吉神宮」「妙法院」
- 5.4 周辺にある「泉涌寺」「雲龍院」「来迎院」「新善光寺」「戒光寺」「即成院」「法音院」「今熊野観音寺」
- 5.5 東福寺周辺にある「東福寺」「勝林寺」「退耕庵」「一華院」「天得院」「同聚院」「正覚庵」「光明院」
- 5.6 伏見にある「伏見稲荷大社」「伏見神寶神社」「荒木神社」「石峰寺」「藤森神社」
- 5.7 その他の【東山・祇園】の神社仏閣をまとめた記事はこちら!
- 5.8 その他の京都の神社仏閣まとめ
- 6 旅ブログ「ちくとりんご」で新緑の京都旅レポ公開中!
寺の概要
- 御本尊:釈迦如来
- 宗派:臨済宗建仁寺派
- 山号:鷲峰山
- 寺号:高台寿聖禅寺
- 創建:1606年
- 開基:高台院(ねね)
御由緒
豊臣秀吉が病死したのは 慶長3年であった。秀吉の正室である北政所(ねね、出家後は高台院湖月心尼)は秀吉の菩提を弔うための寺院の建立を発願し、当初は北政所の実母・朝日局が眠る康徳寺(京都の寺町にあった)をそれに充てようとしたが、手狭であったため、東山の現在地に新たな寺院を建立することになった。秀吉没後の権力者となった徳川家康は、北政所を手厚く扱い、配下の武士たちを高台寺の普請担当に任命した。中でも普請掛・堀直政の働きは大きかったようで、高台寺の開山堂には直政の木像が祀られている。高台寺の開山は慶長11年で、当初は曹洞宗の寺院であった。寛永元年7月、高台寺は臨済宗建仁寺派の大本山である建仁寺の三江紹益を中興開山に招聘。この時、高台寺は曹洞宗から臨済宗に改宗している。
実際の様子
圓徳院を参拝後に高台寺へ向かいました。
▼圓徳院の記事はこちら
台所坂から高台寺を目指します!
晩年のねねも圓徳院(当時のねねの自宅)からねねの道と呼ばれている場所からここを通り、毎日高台寺へ通っていたそうです。
ここは台所坂と呼ばれている緩やかな坂。階段のようになっています。
圓徳院から歩いていく場合は、この台所坂を進んでいくと高台寺への近道になります。
坂の一番上には門がありました!さぁ、ここから高台寺へ向かいますよ〜!
拝観受付へ続く庫裡
台所坂を上った先に、高台寺の庫裡があります。
この写真の正面に写っている建物が庫裡です。庫裡の手前を左へ進んでいくと、高台寺の拝観受付があります。
私は事前に圓徳院で共通拝観券を購入していたので、そちらを窓口で見せて中へ入りました。
高台寺のみ拝観する場合は、受付で拝観料を支払いましょう。この拝観受付の窓口の隣に、高台寺の御朱印の一つを頂くことが出来る窓口があります。
御朱印を頂きたい方は、そちらも合わせてお願いしましょう。
拝観受付後、見晴らしの良い場所に辿り着きます
拝観受付を済ませると、まずは見晴らしの良い開けた場所に着きます。
台所坂を上ってきたことからもわかるように、このお寺は少し高い位置にあるのです。まずは街並みをここから一望するのがオススメです。
ここから見える一見変わった形をした塔は大雲院。金閣寺、銀閣寺と並んで銅閣寺と呼ばれているお寺です。
普段は非公開の建物です。特別拝観期間にのみ、境内へ入ることが出来るそうですよ!
先へ進むと綺麗な新緑の景色が広がります
順路を進みます。
石畳と新緑…なんて素敵な組み合わせ!
その道の先にある趣を感じる茅葺き屋根の小さな建物は遺芳庵と言う名前です。
現在も定期的にお茶会を開く際使われている場所です。
方丈前庭
次は一度靴を脱ぎ、方丈へ向かうのが順路になっています。枯山水庭園になっている方丈前庭。
柳の木が立派です。
ここ、なんか見覚えがあるな〜と思っていたら、秋の夜間特別拝観の時に、プロジェクションマッピングをしていた場所でした!
季節も違いますが、昼と夜だと全然違いますね!
この写真は一度外へ出てから、中門の手前あたりで撮影した写真です。
また違った角度から、この庭園を楽しむことが出来ました。
庭園
方丈への出入り口の近くの写真。
写真の奥に見えているのは開山堂。
その手前に伸びている回廊は観月台です。方丈と開山堂を繋いでいます。
生えている草は芝ですよ!遠目だと一見、苔に見えました。よくお手入れがされているのがわかりますね!
中門
次はこの中門の先を進んでいきます。
先ほど、方丈前庭を別角度から撮影した写真は、この門の近くで撮影しました。
開山堂とその隣にある臥龍池
先ほどちらっと見えていた開山堂。
中に入り参拝することも出来ますが、撮影は禁止です。
開山堂の周辺に広がるのは臥龍池。
この写真に写る木々はほとんどが青紅葉。秋の夜間ライトアップの時は、池にリフレクションした紅葉が楽しむことが出来ます。
臥龍廊
臥龍池にかかる臥龍廊。
池の上にかかる回廊で、橋の役割をしています。私の高台寺の1番のお気に入りスポットです。
しかし立入禁止なので、見て楽しむだけになっています。
この臥龍廊は霊屋に繋がっています。霊屋もお堂内を見ることが出来る場所で、秀吉とねねの像が置かれている場所です。
先へ進みます
開山堂を後にして、順路を進みます。
新緑の季節の石畳。左右には砂利が敷き詰められています。この道を進んでいくと、先ほどの臥龍廊から続いていた霊屋に行くことができます。
霊屋へ続く道とはまた別に、階段があります。
この階段も夜間ライトアップの時に写真を撮った記憶があるなぁ…と思いつつ、この先へ進みます。
時雨亭と傘亭
緩やかな階段が続きます。
その先には傘亭と時雨亭という2つの建物が並んでいます。
この写真は傘亭。茶室です。形が唐傘に似ていることからこの名前が付いています。千利休好みの茶室と言われています。
もう一つの時雨亭は、茶室としては珍しい2階建て。こちらも千利休好みの茶室と言われている建物です。
竹林
二つの茶室を更に進むと、今まで上っていた分、今度は別の道から階段を下ります。すると途中、竹林が見えてきました。
京都の竹林と言えば、嵐山が有名ですが、ここも整備されていて綺麗な竹林でした!
龍の頭と屋根瓦
階段を下り、開山堂周辺まで戻ってきました。
すると途中にインパクトのある龍の頭が!急に頭だけ見つけると、ちょっとびっくりしますね。
この龍の頭の近くは柵があるので、近づく事は出来ません。
さて、ここまできたら高台寺の有料拝観エリアはおしまいです。一番最後に目にとまったのは、外壁の屋根瓦にある高䑓寺の文字。
京都のお寺は、大きくて有名なところは特に、屋根瓦に名前が書いてあり、個性を感じるので、見て見ると面白いですよ!
高台天神
有料拝観エリアを出た後は、すぐ近くにある高台天神へ参拝させて頂きました。
高台天神は、高台寺の御朱印が頂ける場所の一つです。高台寺の拝観受付とは違う御朱印が頂けますよ!
この天神さまは、ねねが高台寺を創建する際、菅原道真公を勧請したのがはじまりです。
まずは手水舎で手を清めます。
こちらが社。
参拝後、隣の建物で御朱印を頂きました!
利生堂で見る涅槃図
最後に寄ったのは利生堂。平成28年に建てられたお堂です。ここは高台寺の礼拝聴聞室でもあります。
ここも御朱印が頂ける場所の一つですよ〜!しかも、お堂内の撮影は自由!と言うことで撮影もさせて頂きました!
現在の人々が死から遠ざかっている姿を感じ、死から逃げずに直視し、静かに瞑想し、安心(心の安らぎ)を得るための場所、命を見つめる場所となるようにとの願いを込めて、建てられたお堂です。
お堂内は全体にとても大きく涅槃図が描かれています。涅槃図とは、お釈迦様が亡くなった時の絵のことを言います。
この涅槃図は、約650年前の作品を最先端の技術を使い、壁に描いていたそうです。
お釈迦様の枕元で悲しむ人々。
悲しんでいる姿が表情から伝わります。
悲しんでいるのは人間だけではありません。
神々やはたまた動物まで、様々な生きとし生けるものが、お釈迦様の死を悲しんでいました。
いかにお釈迦様が慕われていた存在なのかと言うのが伝わってきました。
御朱印
記事内でも度々書いていましたが、御朱印が頂ける場所は全部で3箇所あります。
高台寺拝観受付、高台天神、利生堂の3つです。頂ける御朱印もそれぞれ違います。
値段はそれぞれ300円です。
高台寺で頂ける御朱印
まずは高台寺拝観受付で頂いた御朱印。
「佛心」と書かれた御朱印です。右上には豊臣家の家紋の印があります。
高台天神で頂ける御朱印
高台天神で頂ける御朱印。
「夢」と書かれた御朱印です。こちらの御朱印は秋の夜間ライトアップの時も頂きました。夜間拝観をやっている期間の夜は、この御朱印のみ頂くことができます。
利生堂で頂ける御朱印
利生堂で頂いた御朱印。
「安心」と書かれています。それぞれ違う御朱印、ぜひ高台寺を参拝して、頂いて下さいね!
限定御朱印情報
4月中旬から9月末まで青紅葉限定御朱印が登場します。
そうだ、京都行こうの特別ツアープランに予約した人限定の御朱印です。こちらのツアーで頂くことが出来る御朱印引換券を渡すと、高台寺で限定御朱印を頂くことが出来ます。
夜間特別拝観の時期に限定御朱印が登場します。
暗いところで光る珍しい御朱印です。
最新情報は公式サイトをチェックしてみて下さい。
アクセス
| 住所 | 京都府京都市東山区下河原町526 |
| 電話番号 | 075-561-9966 |
| 拝観時間 | 9:00~17:30(受付終了は17:00)
※夜間特別拝観期間は拝観時間が延長します |
| 拝観料 | 大人 600円
中高生 250円 圓徳院との共通拝観券(※掌美術館も入ることが出来ます) 900円 |
| 御朱印受付時間 | 拝観時間と同じ |
| 駐車場 | 有料 高台寺の拝観券を見せると1時間無料になります |
| 最寄り駅からのアクセス | バスで行くのがおすすめです |
| 公式サイト | こちら |
合わせて訪れたい周辺の神社仏閣情報
東山にある「清水寺」「成就院」「地主神社」「六道珍皇寺」「六波羅蜜寺」「西福寺」「建仁寺」「京都ゑびす神社」「安井金毘羅宮」「若宮八幡宮」「日體寺」「八坂庚申堂」「青龍寺」「法観寺」「圓徳院」「京都霊山護国神社」「銅閣寺」
とても有名な清水寺には舞台だけでなく塔頭寺院や地主神社があります。
少し移動すると六道珍皇寺、六波羅蜜寺、西福寺、建仁寺、京都ゑびす神社、安井金毘羅宮、若宮八幡宮、日體寺、八坂庚申堂、青龍寺、法観寺、圓徳院、京都霊山護国神社、銅閣寺があります。
祇園にある「八坂神社」「仲源寺」「知恩院」「青蓮院門跡」
東山区の一部である祇園エリアに八坂神社、仲源寺、知恩院、青蓮院門跡があります。
京博近くにある「三十三間堂」「法住寺」「養源院」「豊国神社」「方広寺」「智積院」「新日吉神宮」「妙法院」
京都国立博物館周辺に三十三間堂、法住寺、養源院、豊国神社、方広寺、智積院、新日吉神宮、妙法院があります。
周辺にある「泉涌寺」「雲龍院」「来迎院」「新善光寺」「戒光寺」「即成院」「法音院」「今熊野観音寺」
周辺に泉涌寺やその塔頭寺院である雲龍院、来迎院、新善光寺、戒光寺、即成院、法音院、西国三十三観音の札所である今熊野観音寺などがあります。
東福寺周辺にある「東福寺」「勝林寺」「退耕庵」「一華院」「天得院」「同聚院」「正覚庵」「光明院」
東福寺周辺に勝林寺、退耕庵、一華院、天得院、同聚院、正覚庵、光明院など数多くの寺院があります。
伏見にある「伏見稲荷大社」「伏見神寶神社」「荒木神社」「石峰寺」「藤森神社」
伏見周辺に伏見稲荷大社、伏見神寶神社、荒木神社、石峰寺、藤森神社があります。
その他の【東山・祇園】の神社仏閣をまとめた記事はこちら!
この他にも東山・祇園にはたくさんの神社仏閣があります。個別の記事にまとめたので、この周辺で寺社巡りをする際、ぜひ合わせてご活用下さい!
その他の京都の神社仏閣まとめ
その他の京都の神社仏閣をまとめた記事はこちら!
京都はちょっと遠いけど気になる、行ってみたい!と言う人は旅行へ行きましょう!
じゃらんnetはホテルや移動の新幹線、飛行機などを安く予約できる予約サイトです。ぜひ行く際は活用してみて下さいね〜
ちょっと贅沢な旅をしたい人には一休.comがオススメです!
![]()
アマゾンで本を購入して情報収集するのもおすすめですよ~!
旅ブログ「ちくとりんご」で新緑の京都旅レポ公開中!
こちらへ訪れたのは新緑が美しい5月。もう1つの運営ブログであるちくとりんごで、この時の旅行レポを公開中です!
ぜひこちらも参考にしてみて下さい!
参考
【京都旅行ブログ】2泊3日の京都旅行!新緑の季節の京都旅は超癒し #2ちくとりんご
広告
![]()
にほんブログ村