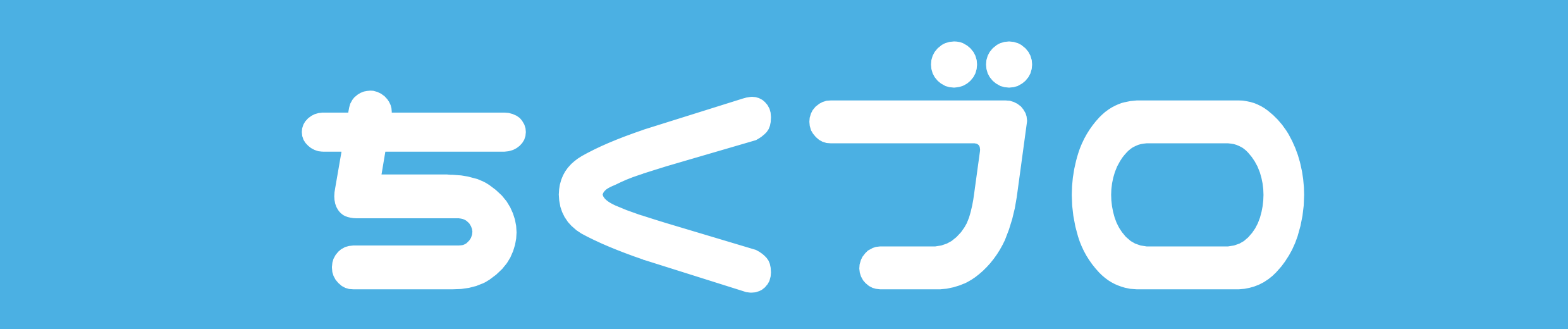ども!ちく(@chikuchanko)です。
今回紹介するのは紅葉の名所として名高いお寺東福寺です!臨済宗東福寺派の大本山で、京都五山の大伽藍です。
八相の庭や通天橋から見る景色が綺麗なことで有名です。
京都駅から電車で1駅、東福寺駅から近い場所にあるお寺で、だいたい京都駅と伏見稲荷大社の間にあります。
 ちく
ちく
早速紹介していきます!
目次
- 1 寺の概要
- 2 実際の様子
- 3 御朱印帳と御朱印
- 4 アクセス
- 5 合わせて訪れたい周辺の神社仏閣情報
- 5.1 東福寺周辺にある「東福寺」「勝林寺」「退耕庵」「一華院」「天得院」「同聚院」「正覚庵」「光明院」
- 5.2 周辺にある「泉涌寺」「雲龍院」「来迎院」「新善光寺」「戒光寺」「即成院」「法音院」「今熊野観音寺」「新熊野神社」
- 5.3 伏見にある「伏見稲荷大社」「伏見神寶神社」「荒木神社」「石峰寺」「藤森神社」
- 5.4 京博近くにある「三十三間堂」「法住寺」「養源院」「豊国神社」「方広寺」「智積院」「新日吉神宮」「妙法院」
- 5.5 東山にある「清水寺」「地主神社」「六道珍皇寺」「六波羅蜜寺」「西福寺」「建仁寺」「京都ゑびす神社」「安井金毘羅宮」「若宮八幡宮」「日體寺」「八坂庚申堂」「青龍寺」「法観寺」「高台寺」「圓徳院」「京都霊山護国神社」「銅閣寺」
- 5.6 祇園にある「八坂神社」「仲源寺」「知恩院」「青蓮院門跡」
- 5.7 その他の【泉涌寺&東福寺&伏見】の神社仏閣をまとめた記事はこちら!
- 5.8 その他の京都の神社仏閣まとめ
- 6 旅ブログ「ちくとりんご」で新緑の京都旅レポ公開中!
寺の概要
- 御本尊:釈迦如来
- 宗派:臨済宗東福寺派
- 山号:慧日山
- 寺号:東福寺
- 創建:1236年
- 開基:九条道家
- 開山:聖一国師
御由緒
嘉禎2年、九条道家は、この地に高さ5丈(約15メートル)の釈迦像を安置する大寺院を建立することを発願、寺名は奈良の東大寺、興福寺の二大寺から1字ずつ取って「東福寺」とした。
実際の様子
臥雲橋を通って境内を目指します
東福寺三名橋の一つである臥雲橋。ここは無料で通ることが出来る場所です。ここからの眺めも十分綺麗だと思えるほど、新緑の季節の青紅葉がたくさん並んでいます。
ここを渡って東福寺へ向かいます。この写真では、奥には通天橋も見えています。
日下門から境内へ!
東福寺の境内へこの日下門から入ります。
この門は16:30〜次の日の8:30まで閉門されているので、この時間は境内へ立ち入ることが出来ません。時間に注意して行きましょう!
重要文化財 禅堂
日下門を入ると、まず目にとまるのがこの禅堂。門をくぐると、左手にあります。
日本最古最大の中世から遺る唯一の座禅道場です。
国宝 三門
東福寺の三門。本来は、お寺の入口となる場所(神社で言う鳥居)です。「山門」ではなく「三門」と書いて「さんもん」と読みます。
三門は、空門、無相門、無作門の三解脱門の略で、本来は三戸をすべて開くのが基本とされています。東福寺の三門は、五間三戸の二重門で、左右に上へ続く階段である山廊があります。
こちらは国宝に指定されています。
仏殿(本堂)
本堂はこちら。こちらは仏殿、法堂とも呼ばれています。三門のすぐ奥にあります。
参拝はこちらへさせて頂きました。本堂内へ入ることは出来ないのですが、扉から御本尊のお顔や天井絵を少し見ることが出来ます。
天井絵の蒼龍は、御朱印帳のデザインにもなっています。毎年3月14日から16日に涅槃会が行われます。その時のみ、大涅槃図が公開されます。
五社成就宮
東福寺の鎮守社である五社成就宮。八幡社、日吉社、賀茂社、稲荷社、春日社の5社から成り立っています。
場所は三門の横あたりです。
この連なる鳥居の先を進んでいきます。
緩やかな階段の先に社があるので、こちらへお参りさせて頂きました。
参拝後、まずは有料エリアの一つ 方丈(八相の庭)へ!
方丈を拝観する為には、この庫裡で拝観受付を済ませなければいけません。
拝観受付のすぐ近くに御朱印受付もあるので、東福寺で御朱印を頂く場合もこちらへ寄りましょう。
 ちく
ちく
庫裡から方丈へ続く回廊
方丈の魅力は何と言っても八相の庭。東西南北、方丈を中心に四方を囲っている庭園です。それぞれ東庭、西庭、南庭、北庭があります。
この記事では、東庭、南庭、北庭を紹介しています。
創建時代の鎌倉時代らしい質実剛健な庭園の雰囲気と近代禅宗庭園の雰囲気が絶妙に混ざり合っている、世界から注目されている庭園です。
庭園に向かう為、庫裡から続く回廊を歩いていきます。
回廊良いな〜!見てるだけで幸せ…
この回廊の途中に、八相の庭の1つである東庭があります。
円柱のような形をした石は、北斗七星を構成をしています。このことから北斗の庭とも呼ばれているのです。
南庭
回廊を進んでいくと、方丈へ辿り着きます。方丈から見ると、まず目の前に広がるのは南庭です。
庭園の奥に見えているのは恩賜門。その前には巨石が並んでいます。それぞれに名前があり、合わせて四仙島と呼ばれています。
東福寺の中でも有名な枯山水庭園です。
ゆっくり座って、この庭を眺めている人も多くいました。日本らしい庭園の景色が魅力的な庭です。
通天台から見る通天橋
南庭から順路を進むと、通天台と言う見晴台があります。
ここから東福寺三名橋で最も有名な通天橋を見ることが出来るのです。
こちらがその通天台。ここを撮るだけでも青紅葉が映えて絵になるのは、さすがの一言です。
通天台からみる通天橋。
青紅葉の奥に見えています。
市松模様の敷石が特徴の北庭
通天台から更に順路を進みます。すると、北庭に着きました。
苔と敷石が市松模様になっているのが特徴の庭です。
緑の苔はウマスギゴケと言う品種です。
敷石は、南庭にある恩賜門に使われていた石を敷き詰めて作られています。この北庭の市松模様も、東福寺の中で有名な景色の1つです。
青紅葉と紅葉を満喫出来る通天橋へ!
方丈を満喫したので、次はもう1つの有料エリアである通天橋へ向かいます。
拝観料を支払い、受付を進むと、すぐに橋へ着きます。
ここは通天橋の中央あたりにある見晴台。
臥雲橋から少し突き出して見えていた場所です。
この橋から見る景色は、どこからどこを見てもとっても素敵!
つい立ち止まってゆっくり見て、写真を撮りたくなってしまいますね。
重要文化財 開山堂(常楽庵)
通天橋の先を進みます。
するとゆるやかな階段になっていました。
この先にあるのは開山堂と言うお堂です。
開山堂には、東福寺を開山をした聖一国師がお祀りされています。
この開山堂は、東福寺境内でも一番最初に高い位置にあるお堂です。
お堂周辺は借景庭園です。
四方に広がる自然の景色と共に、お堂周辺の景色を楽しみましょう。
5月中旬はツツジが咲いているのが特徴的でした。
もう1つの注目ポイントはこの砂紋。
八相の庭の市松模様を思い出します。特徴的な四角い模様が素敵です。
愛染堂
通天橋は、開山堂と反対方向にもう1つ進む道があります。その先にあるのがこの愛染堂。その名の通り愛染明王を祀っているお堂です。
曇っていたのですが、このお堂の近くへ行った時は晴れてきて素敵な写真を撮ることが出来ました。
愛染明王は、恋愛にご利益のある仏様です。縁結びなど、恋愛に関係のあるご利益を頂きたい方はとくに、このお堂も合わせて参拝してみて下さい。
緑の中から見る通天橋
愛染堂の近くに、東福寺三名橋のかかる渓谷へとつながる階段があります。
その階段を降りた先からは、また違った角度で通天橋を見ることが出来ました。
渓谷 洗玉澗
橋のかかっている渓谷の写真。
東福寺の中でも一番涼しい場所です。
この写真に写っているのは臥雲橋の土台。橋を違う角度から楽しめるのも、この渓谷へ降りる1つの魅力です。
通天橋周辺の有料エリア、最後は階段を上って、通天橋周辺の青紅葉を更に楽しみます。
新緑の季節の青紅葉を満喫!
通天橋周辺は、青紅葉が広がっています。
とっても綺麗な青紅葉の景色…見ていると時間を忘れてしまう…
目の保養になる優しい新緑の緑が良い雰囲気を出していました。
きっと紅葉の季節は、ここが一面オレンジ色になるのでしょう。それはそれでまた綺麗な景色になりそうですね!
余談ですが、東福寺の屋根には「東福寺」と書かれています。その間には山号の「慧日山」の文字も。
瓦もよく見てみると、発見が出来ますよ〜!
偃月橋と龍吟庵
最後に、庫裡の裏手にある東福寺三名橋の1つ偃月橋へ向かいました。
偃月橋は、まるで回廊のようでとっても素敵です。
3つの橋の中で一番人が少なかったです。と言うより、気付いてない人も多いのかも?
その奥にあるのは東福寺の塔頭の一つである龍吟庵です。
ここは特別公開の日のみ、中へ入ることが出来るようです。
御朱印帳と御朱印
御朱印帳と御朱印は庫裡にある御朱印受付で頂くことが出来ます。
蒼龍のオリジナル御朱印帳
東福寺オリジナル御朱印帳はこちら。
値段は1500円。
本堂の天井絵である蒼龍の御朱印帳です。
御朱印
オリジナル御朱印帳を購入すると1ページ目が見開であらかじめ書かれています。
左のページに「禅心」という言葉の墨書き。右のページに東福寺の由緒が書かれています。
御朱印はこちら。
値段は帳面に墨書きで書いて頂く場合500円、墨書きではなくスタンプで中央の文字を押して頂く場合300円。
中央に「大佛賽殿」と書かれています。中央の上に押されている印は、東福寺の寺紋である九条家下り藤です。
限定御朱印情報
青紅葉が見頃の時期になると限定御朱印が登場します。
紅葉シーズンになると限定御朱印が登場します。
最新情報は公式サイトのお知らせをチェック!
アクセス
| 住所 | 京都府京都市東山区本町15-778 |
| 電話番号 | 075-561-0087 |
| 開門時間 | 4月~10月 9:00~16:00
11月~12月初旬 8:30~16:00 12月初旬~3月 9:00~15:30 |
| 拝観料 | 東福寺本坊庭園(方丈) 大人 400円/小中高生 300円
通天橋・開山堂 大人 400円/小中高生 300円 |
| 御朱印受付時間 | 開門時間と同じ |
| 駐車場 | 無料 |
| 最寄り駅からのアクセス | JR奈良線・京阪電車「東福寺駅」より 徒歩10分 |
| 公式サイト | こちら |
合わせて訪れたい周辺の神社仏閣情報
東福寺周辺にある「東福寺」「勝林寺」「退耕庵」「一華院」「天得院」「同聚院」「正覚庵」「光明院」
東福寺周辺に勝林寺、退耕庵、一華院、天得院、同聚院、正覚庵、光明院など数多くの寺院があります。
周辺にある「泉涌寺」「雲龍院」「来迎院」「新善光寺」「戒光寺」「即成院」「法音院」「今熊野観音寺」「新熊野神社」
周辺に泉涌寺やその塔頭寺院である雲龍院、来迎院、新善光寺、戒光寺、即成院、法音院、西国三十三観音の札所である今熊野観音寺、新熊野神社などがあります。
伏見にある「伏見稲荷大社」「伏見神寶神社」「荒木神社」「石峰寺」「藤森神社」
伏見周辺に伏見稲荷大社、伏見神寶神社、荒木神社、石峰寺、藤森神社があります。
京博近くにある「三十三間堂」「法住寺」「養源院」「豊国神社」「方広寺」「智積院」「新日吉神宮」「妙法院」
京都国立博物館周辺に三十三間堂、法住寺、養源院、豊国神社、方広寺、智積院、新日吉神宮、妙法院があります。
東山にある「清水寺」「地主神社」「六道珍皇寺」「六波羅蜜寺」「西福寺」「建仁寺」「京都ゑびす神社」「安井金毘羅宮」「若宮八幡宮」「日體寺」「八坂庚申堂」「青龍寺」「法観寺」「高台寺」「圓徳院」「京都霊山護国神社」「銅閣寺」
とても有名な清水寺には舞台だけでなく塔頭寺院や地主神社があります。
少し移動すると六道珍皇寺、六波羅蜜寺、西福寺、建仁寺、安井金毘羅宮、若宮八幡宮、日體寺、八坂庚申堂、青龍寺、法観寺、高台寺、圓徳院、京都霊山護国神社、銅閣寺があります。
祇園にある「八坂神社」「仲源寺」「知恩院」「青蓮院門跡」
東山区の一部である祇園エリアに八坂神社、仲源寺、知恩院、青蓮院門跡があります。
その他の【泉涌寺&東福寺&伏見】の神社仏閣をまとめた記事はこちら!
この他にも泉涌寺&東福寺&伏見にはたくさんの神社仏閣があります。個別の記事にまとめたので、この周辺で寺社巡りをする際、ぜひ合わせてご活用下さい!
その他の京都の神社仏閣まとめ
その他の京都の神社仏閣をまとめた記事はこちら!
京都はちょっと遠いけど気になる、行ってみたい!と言う人は旅行へ行きましょう!
じゃらんnetはホテルや移動の新幹線、飛行機などを安く予約できる予約サイトです。ぜひ行く際は活用してみて下さいね〜
ちょっと贅沢な旅をしたい人には一休.comがオススメです!
![]()
アマゾンで本を購入して情報収集するのもおすすめですよ~!
旅ブログ「ちくとりんご」で新緑の京都旅レポ公開中!
こちらへ訪れたのは新緑が美しい5月。もう1つの運営ブログであるちくとりんごで、この時の旅行レポを公開中です!
ぜひこちらも参考にしてみて下さい!
参考
【京都旅行ブログ】2泊3日の京都旅行!新緑の季節の京都旅は超癒し #3ちくとりんご
広告
![]()
にほんブログ村